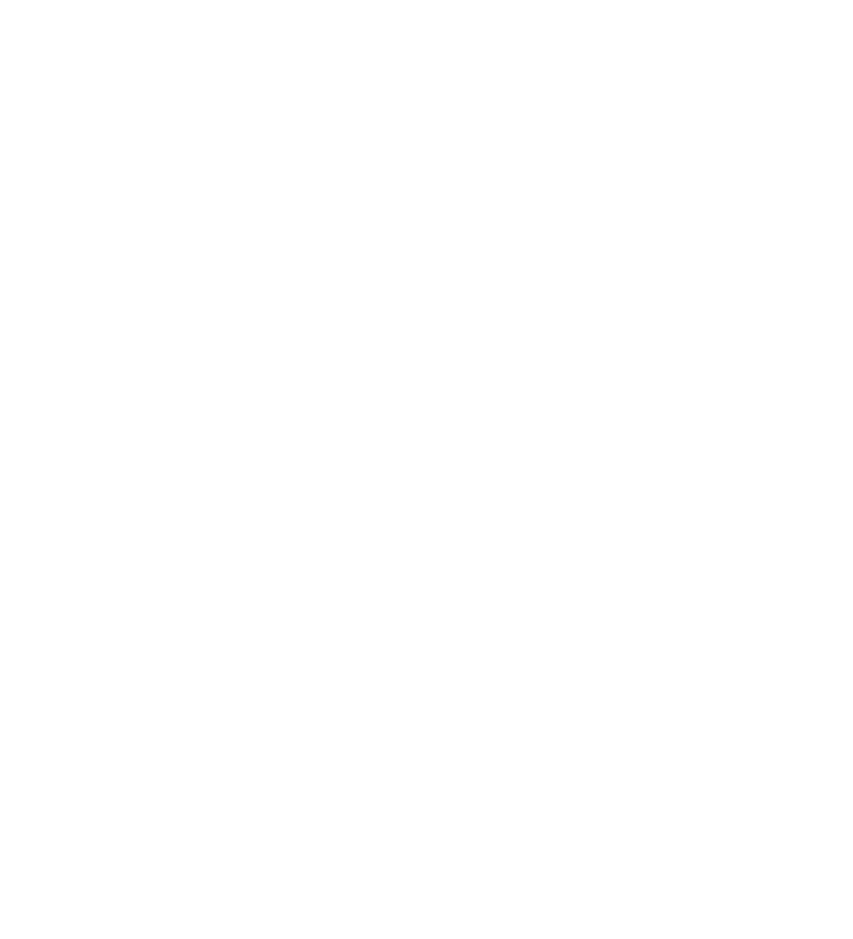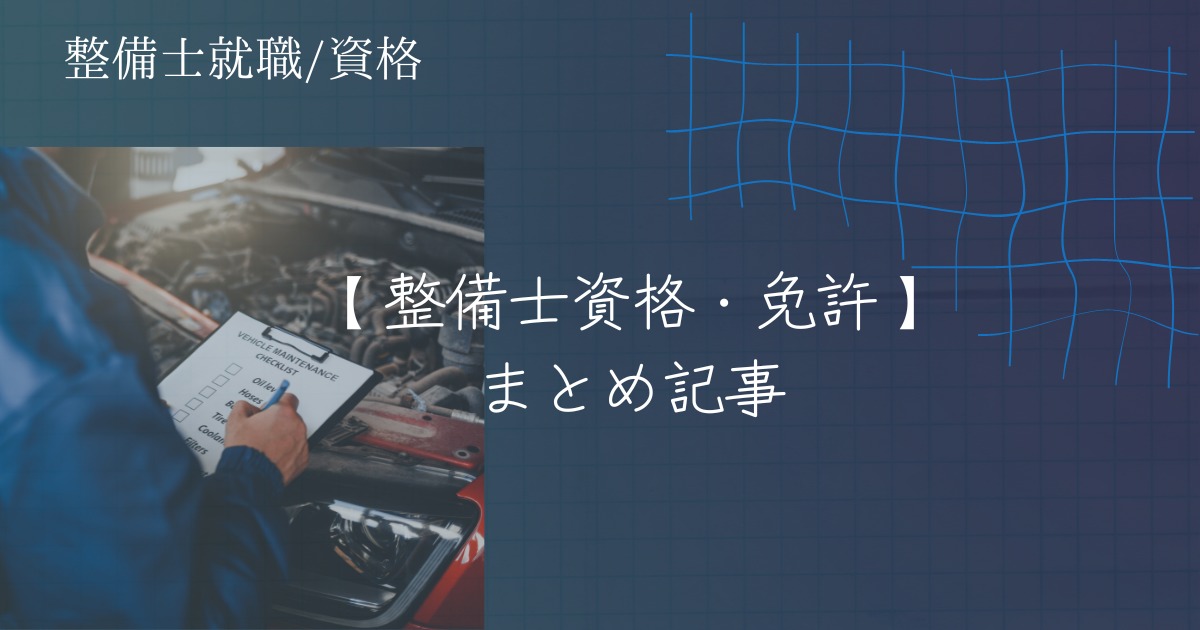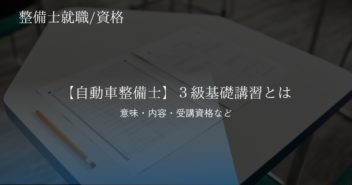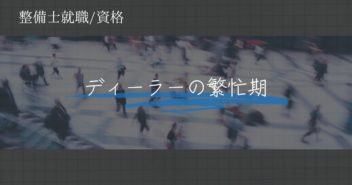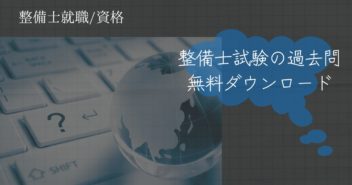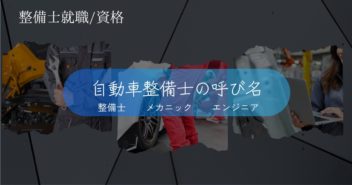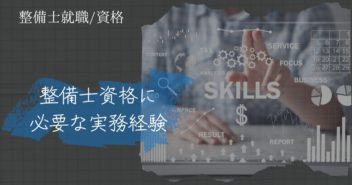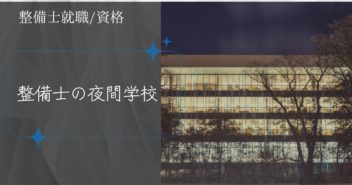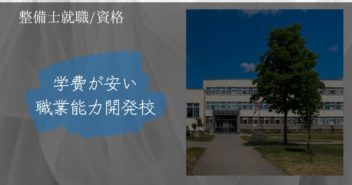- 自動車整備士の資格にはどんな種類があるのか
- 資格によって仕事内容の違いや役割があるのか
- 持っている資格によってどのくらい給与が変わるのか
- それぞれの資格を取る方法や受験資格が知りたい
- 自動車整備士の資格について一から知りたい
この記事では、これまで長く自動車整備業界にたずさわり、自らも一級整備士の資格を持つ管理人が、自動車整備士資格についての全てをわかりやすく解説します。
この記事を書いた人:きりん
元ディーラーの一級整備士で整備士ねっと管理人です。自動車整備業界に長く携わり、現在は整備業界のコンサルなども行っています。twitterでたくさんの整備士さんや業界の人と繋がっているのでチェックしていただけるとうれしいです。(seibisi_net)
自動車整備士の資格・免許
自動車整備士の資格には大きく分けて「国が認定する国家資格」と、「その他の資格」に分けられます。最も重要な資格は国家資格です。現在、日本の自動車整備士の約 60~80%程度が、3級以上の整備士の資格を持って働いていると言われています。
自動車整備業界の様々な制度も、この国家資格制度を基に作られているため、この記事では国家資格について説明します。
※自動車整備士は資格で、免許ではありません。
自動車整備士の国家資格の種類(正式名称)
整備士の資格は「1級、2級、3級、2輪、特殊」に大きく分かれ、さらに細かくガソリンやジーゼルなどに分かれています。
| 分類(級) | 種目(正式名称) |
|---|---|
| 一級整備士 | 一級小型自動車整備士 一級大型自動車整備士 一級二輪自動車整備士 |
| 二級整備士 | 二級ガソリン自動車整備士 二級ジーゼル自動車整備士 二級自動車シャシ整備士 |
| 三級整備士 | 三級自動車ガソリン・エンジン整備士 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士 三級自動車シャシ整備士 |
| 二輪整備士 | 二級二輪自動車整備士 三級二輪自動車整備士 |
| 特殊整備士 | 自動車車体整備士 自動車電気装置整備士 自動車タイヤ整備士 |
| その他 | 自動車検査員 |
※現在、一級大型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、タイヤ整備士試験は実施していませんので、事実上取得することはできません。
受験資格
資格取得にはそれぞれその経験やスキルに応じた試験があり、受験資格があります。もちろん最初から1級を受験することはできません。
例えば2級整備士の受験資格は、下記のとおりです。
3級を取ってから3年以上働いた経験がある者
受験資格について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。
整備士の資格によってできることの違い
自動車整備士の仕事は、資格の有無によって、できる仕事やできない仕事があり、役割があります。それは、法律に基づいたもので、本来できないことをやってしまえば、違法行為となります。
また、3級→2級→1級と進むにつれて、会社での立場は上位になるのが普通で、できることも増えてきます。
それでは資格別の主な役割や、できることについて表で説明します。
| 資格なし | 三級整備士 | 二級整備士 | 一級整備士 | |
|---|---|---|---|---|
| (1)整備士として働く | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| (2)工場に必要な整備士の数として数えられる | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| (3)整備主任者になることができる | ー | ー | 〇 | 〇 |
| (4)自動車検査員になれる | ー | ー | 〇 | 〇 |
| (5)電子制御装置整備の整備主任者になれる | ー | ー | 〇 (講習・試験必要) | 〇 (無条件) |
| (6)整備工場の開業 | ー | ー | 〇 | 〇 |
- 2級整備士になるとたくさんのメリットがある
- 3級整備士のメリットはほとんどなく、2級整備士になるための布石
- 1級整備士と2級整備士の違いはほとんどない
自動車整備業界では一般的に「二級整備士で一人前」と呼ばれる風潮があり、若い整備士のほとんどが、2級整備士を目指して3級整備士の資格を取得しています。(2級を取るためには、基本的に3級取らなければならないため)
経営者側からみても、2級整備を多く雇用することが、会社の大きなメリットになります。また、個人の就職・転職の際にも2級整備士の資格をもっているととても有利になります。
一級小型自動車整備士とは
1級整備士は、平成になってから運用を開始したもので、まだまだメリットが少なく、「1級を取得する必要があるの?」という論調があります。
しかし、1級整備士は自動車整備についての知識や技術が最も高いことが認められる最高峰の資格であり、業界人の間では、心理的に二級整備士とは大きく区別されてます。
1級の試験で求められる能力には次のようなものがあります。
- あらゆる自動車制御装置の高い知識
- 高い故障診断技術
- 新技術(ハイブリッドや電気自動車など)に対する知識
- 環境保全に対する知識
- 安全管理に対する知識
(1)整備士として働く

資格がなくとも整備士として働くことができます
一般的にあまり知られていないのですが、資格がなくとも整備士になることが可能です。実際に資格をもっていない状態で、整備工場で働いている人が数多くいます。
また、無資格で働きながら、3級→2級→1級と働きながらステップアップしていく制度があり、高校卒業と同時に無資格で就職し、1級まで取ることができます。
詳しくはこちらの記事に書きました。
(2)工場に必要な整備士の数として数えられる
整備工場を営むには、全工員の1/4(よんぶんの1)以上が国家資格を持った整備士でなければならない
上記が法で定められていて、無資格の整備士と3級整備士の大きな違いです。この法があるために、企業サイドから見ると資格を持っている人を雇用する大きなメリットがあります。
この場合の「整備士」は3級以上であれば良いことを指します。
例えば、整備工場で整備士の資格を持っている人が少なくなり、この基準を下回ってしまうと、工場の経営が存続できなくなります。経営者側から見ると資格を持っていない人よりも、資格を持っている人の方が採用しやすい、有利、ありがたい、となります。
企業側(整備工場)にとって、3級整備士は「整備士」として認められることで「整備工場の整備士の数」という基準をクリアできるという役割があります。
一方で、従業員である個人にとっては、資格手当(給与)が付くなどのメリットはあるものの、それほど大きなメリットにはなりません。
但し、三級の取得は、二級整備士を取得するステップという役割があります。専門学校等に通わない限り、二級整備士を取得するには、三級整備士の資格を取らなければならないからです。
国は3級整備士以上の資格を持っている人を「自動車整備士」、国家資格を持っていない人で整備工場で働く人を「整備要員(工員)」などと呼び、整備士とは分けています。
(3)整備主任者になることができる
2級整備士以上になると、特定整備の整備主任者になることができます。
整備主任者とは、その工場の責任者のようなもので、誰かが整備した車両について、確実な整備を実施したかをチェックする仕事をします。国が認めている責任のある資格であり、万が一整備後に、整備不良による事故があった場合には、責任を取ることになる重要な仕事です。
(4)自動車検査員になることができる
2級整備士以上で、自動車検査員になることができます。(教習、試験あり)
自動車検査員とは、民間車検場(自ら車検ができる大きな整備工場「指定工場」)において、国の検査官に代わって自動車の検査ができる資格です。
その責務は大変重要なもので、不正を犯した場合(本来車検に通らない自動車を車検に通すなど)には、「罰則は公務員に準ずる」となっており、国のホームページにも名前が掲載されたりします。
しかし、その分「資格手当」が大きく、給与に大きな差がつく資格になっています。
なお、指定工場でない工場(認証工場)では、2級整備士を持っていてもなることができません。
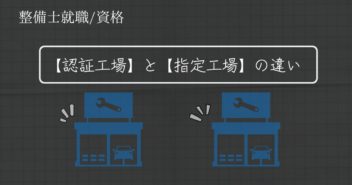
(5)電子制御装置整備の整備主任者になれる
これは、令和2年4月1日に施行された新しい制度(特定整備制度)による整備主任者です。
1級整備士の資格を持っていると無条件でなることができます。二級整備士は、講習や試問を受けることでなることができます。
上記表の、「(3)の整備主任者」と大きな違いはありませんが、詳細はここでは割愛します。
(6)整備工場の開業
独立・開業には、実質二級整備士が必要
整備工場には、前述した「整備主任者」が最低一人必要です。そして、整備主任者には2級整備士以上を持っていなければなることができません。
整備工場を開業したい場合は、自らが2級整備士の資格を持っているか、2級整備士の資格を有する人を雇用しなければなりません。
小さい整備工場から開業したい場合、2級の資格を持った整備士を雇うことが困難であるケースが多く、大抵の場合は自らに2級整備士の資格が必要になります。
各資格による手当(給与の違い)

- 3級整備士 → 1,000円~3,000円程度
- 2級整備士 → 3,000円~5,000円程度
- 1級整備士 → 5,000円~10,000円程度
- 整備主任者 → 1,000円~3,000円程度
- 自動車検査員 → 2,000円~15,000円程度
手当に関しては、会社によって大きく違いますが、概ね上記のようになります。一般の方には、案外少ないと思われるかもしれませんが、特にディーラーにおいては、ほとんどの整備士が2級整備士の資格を持っており、言わば当たり前となっているため、それほど特別な手当が出るわけではありません。
整備士の給与については、こちらの記事で詳しく説明しています。
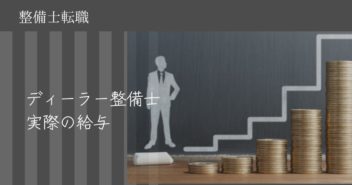
資格試験の学科試験
整備士の試験は基本的に「学科試験」と「実技試験」に合格しなければなりません。
それぞれの資格の「学科試験」の合格率や難易度については別記事で説明していますので、そちらをご覧ください。
資格試験の実技試験
実技試験には免除規定があるため、免除される人がほとんどで、実技試験を受験される人自体が非常に少ない現状があります。そのため、どこでどんな内容の試験が実施されているかについて、わからない人が多いと思います。
実技試験についてはこちらの記事で詳しく説明しています。
資格試験の受験方法
筆記試験の実施日は、10月と3月の年2回。申込みは2ヶ月前
資格試験の受験方法や必要な書類についてはこちらの記事に詳しく書きました。
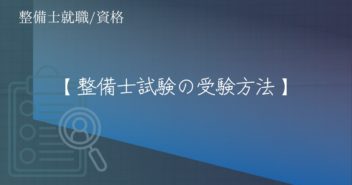
教科書・練習問題の購入方法
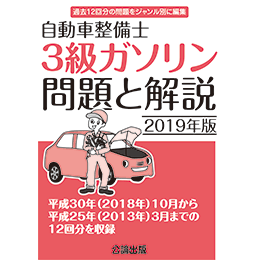
教科書・練習問題は、町の本屋さんではなかなか買うことができません。購入方法についてはこちらをご覧ください。
その他の国家資格
二輪自動車整備士

自動車の中でもオートバイなどの2輪自動車についての資格です。
3級と2級があり、3級は基本的な整備を、2級は3級の上位資格です。
2輪車の取扱いが多い整備工場で必要とされる資格となっていますが、二輪車に特化したこの資格を持っていなくとも、3級ガソリンや2級ガソリンの資格を持っていれば、事実上二輪車の整備ができる制度になっているため、取得している人はあまり多くはありません。
二輪車の資格を持っていても、四輪車の整備は出来ませんが、四輪車の資格を持っていると二輪車の整備ができます。3級ガソリン、2級ガソリンなどの、普通の四輪車の資格を持つことが最も重要であることがわかります。
特殊整備士

その他の資格として、「自動車車体整備士」「自動車電気装置整備士」「自動車タイヤ整備士」の3つの特殊整備士の資格があります。
しかしこの中の「自動車車体整備士」以外は、現在ほとんど機能しておらず、試験すら長らく実施していない状況になっています。
車体整備士については、自動車整備のうち、「板金・塗装」に必要な資格となっており、この資格は板金整備を行う人が取得するケースがあります。
「特殊」というのは、「特別な」という意味ではなく、「限定的な」という意味で捉えるとわかりやすいです。
例えば、「自動車電気装置整備士」は自動車の中の電気の分野だけを切り取った、限定的な資格となっているため、今ではほとんど需要がありません。
まとめ
自動車整備士の仕事をする上で、整備士の資格はとても大事です。自分の経験にあわせて、計画的に資格を取得してステップアップすることが大事です。
以上、自動車整備士資格のまとめ記事でした。