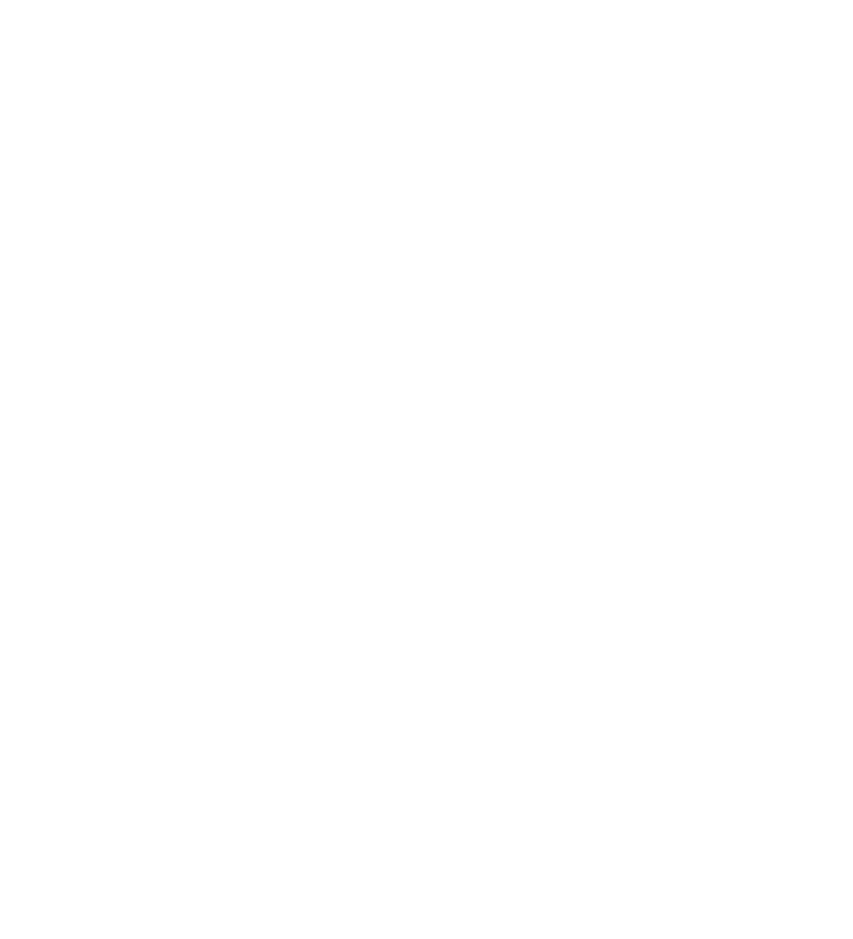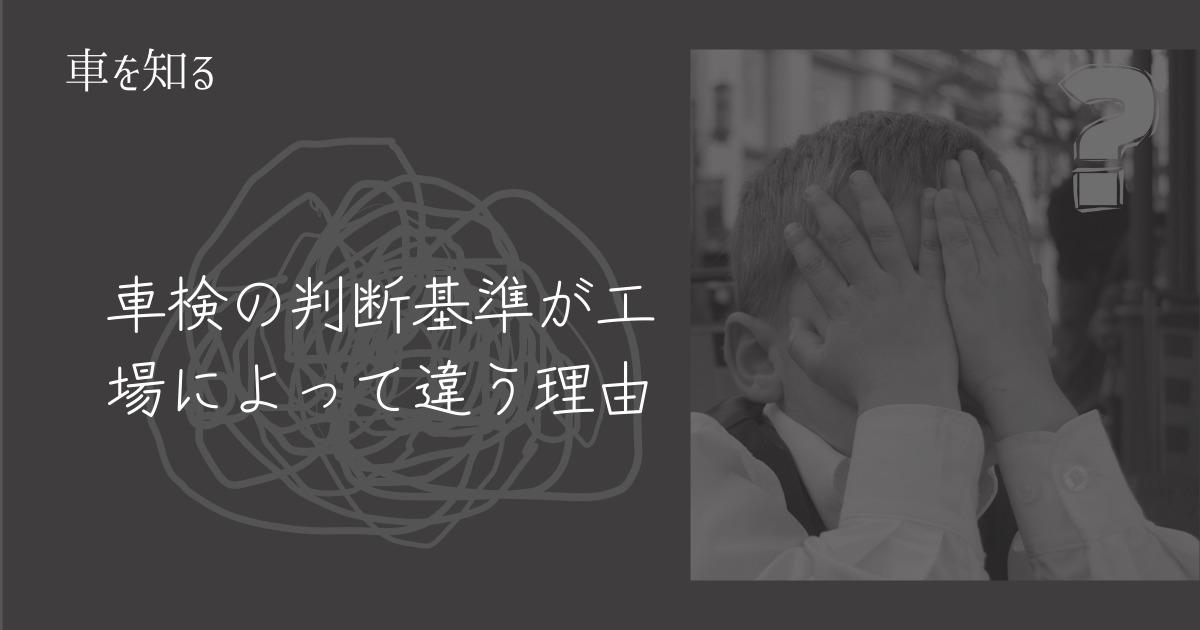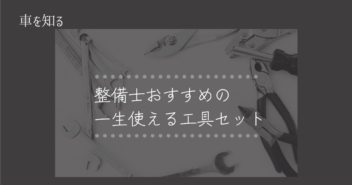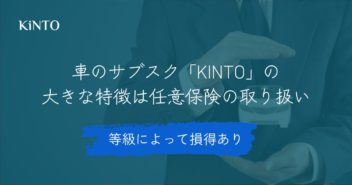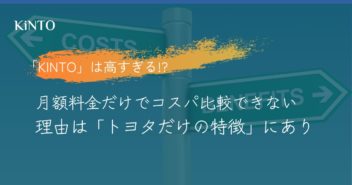- 「前回の車検では何も言われなかったのに、今回は車検とおらない?」
- 「車検対応って書いてある部品を装着しているのに車検がとおらない?」
こういう事があると、ちょっと心穏やかではいられないですね。
そんな、車検の「とおる・とおらない・判断が違う」の疑問について元ディーラーの一級整備士が詳しく解説します。
結論:車検に通る通らないは、整備工場によって変わります。
この記事を書いた人:きりん
元ディーラーの一級整備士で整備士ねっと管理人です。自動車整備業界に長く携わり、現在は整備業界のコンサルなども行っています。twitterでたくさんの整備士さんや業界の人と繋がっているのでチェックしていただけるとうれしいです。(seibisi_net)
車検の検査を実施する場所は2パターン

- 国の検査場
- 民間の整備工場(指定工場という)
上記の2つの場所で判断基準が違う可能性がありますので、はじめにこの2つの違いを説明します。
1.国の検査場で検査するパターン
認証工場に車検を依頼した場合
あなたが認証工場と呼ばれる整備工場に車検を依頼した場合、整備工場ではエンジンやブレーキの点検整備を実施した後に、車両を国の検査場に持ち込みます。
国の検査場で、国の検査官によって基準に適合するかの検査をすることになります。検査に合格すれば車検が終わり、また車を公道で使用することができるようになります。
2.民間の整備工場で検査するパターン
指定工場に車検を依頼した場合
あなたが指定工場と呼ばれる整備工場に車検を依頼した場合、その工場で検査を実施します。
指定工場とは、車検の検査をする事が許されている民間の整備工場です。
ディーラー等の比較的規模の大きい整備工場が指定工場にあたり、さまざまな厳しい基準をクリアした整備工場です。
指定工場には「自動車検査員」の資格を持った整備士が在籍しており、自動車検査員は国の検査官に代わって、車両が基準に適合しているかを検査する事ができます。
つまり、指定工場とは国の検査場に車両を持って行かなくても、自分たちの整備工場と社員で検査を実施できる、国に信頼されている整備工場です。
車検の検査をする場所の2パターンは、国の検査場で、国の検査官が検査する場合と、民間の整備工場で自動車検査員の資格を持った人が検査する場合がります。
あなたがいつも依頼する整備工場はこのどちらのパターンかがわかりますか?気になる人はぜひ調べてみてください。
車検とは
車検とは、公道を走る自動車が、国の基準に適合しているか・していないかを一定期間ごとに検査するもの
国の基準とは、保安基準と呼び、自動車の安全や環境を守るために定められています。
車検に合格するかしないかの判断は、この保安基準を満たしているか・いないかで判断されることになり、そのために実際に車両を目視や検査機器を使って検査しています。
工場によって判断が違う理由

- 法解釈の違い
- 法を知らない・勘違い
検時に保安基準に適合するかを検査する場所(人)は2パターンあることを前述しましたが、両者とも基本的にその判断は絶対です。
しかし、車検の基準(保安基準)とは法令であり、文章表現であるため、その解釈は検査する人間によって違う場合があるのも事実です。
例えば、「車枠(しゃわく)及び車体は、著しく損傷していないこと」と、保安基準で定められていますが、「著しい損傷」というのは具体性を欠いており、どこがどうなっていれば著しい損傷と言えるのかどうかは正に検査員の判断です。
この、法の解釈の違いこそが車検の合格・不合格の違いに表れます。
国の検査場は全ての都道府県に1つ以上あり、検査官は数千人います。同じ国の検査場でも、大阪の検査場では合格するのに、東京の検査場では不合格になるなんてことも当然にありえます。そして、民間の車検場(指定工場)では、なおさら違いが出やすいです。
一方で、民間の検査場(指定工場)では、明らかに間違った法解釈や勘違いをしている場合があります。
民間の検査場(指定工場)で違いが出やすい理由
民間の検査場(指定工場)は慎重→判断が厳しい
指定工場では、もし、適合していないような自動車に対し、合格させてしまうようなことがあると、その指定工場の資格を取り上げられるなどの、厳罰を受ける可能性があります。指定工場では保安基準の判断は慎重にならざるをえません。
判断に迷ってしまった時には、とりあえず不合格と判断しておけば、おとがめを受ける可能性は無いので「不合格にしよう」と、なりやすいことは容易に察することができます。
民間の指定工場では、グレーを黒にする傾向がある
これは、国の検査場よりも民間の指定工場のほうが厳しい検査をする可能性があることを指しています。
「○○ディーラーでは車検に受からないと言われたのに、国の検査場では何も言われなかった。」という話は本当によく聞きます。
しかし、これはしかたががない事なのかもしれません。指定工場は自分たちの身を守るため、危ない橋を渡る訳にはいかないという事情があります。
白黒はっきりさせることには、そもそも限界がある
ここまでの説明で、整備工場によって車検に合格・不合格の違いがでる理由がわかったでしょうか。どこで検査しても同じ結果にすることは理想ですが、難しいのが現実です。
保安基準を今よりももっともっと細かく判断基準まで具体的に明記していけば、違いは生まれにくくなりますが、自動車というものは製作された年代やメーカー、タイプなどにより、構造が大きく違うため、それにも限界があります。
また、高度化するスピードが早すぎる自動車業界において、新たな構造の自動車や新たな装置を搭載した自動車が次々と登場します。
それら自動車技術の高度化に、法整備が追いついていけないのも現実です。
不服がある場合

徹底的に説明を聞く
- 「前回はこれで車検に合格したのに、今回は修理しないと合格できないと言われた!」
- 「車検対応と書いてある商品を装着したのに合格できないと言われた!」
など、納得できない場合もあると思います。それを修理するのに、高額な整備が必要となれば、なおさら不服になります。
そんな時には、なぜ車検に合格できないのか、どうすれば合格できるのか、他に方法はあるのか、必ず明確な理由があって、合格できないと判断されているので、その理由を聞きましょう。
これをはっきりと説明できないのであれば、適当にごまかされている可能性があるので、こと細かに説明を聞いてください。これを説明するのは整備工場や検査員の義務です。
その説明で、明らかに不合格な案件だと自分で納得できればあきらめるしかなさそうですね。
もしあなたがグレーゾーンで不合格だと言われていると感じたら、他の指定工場に依頼すれば合格になる可能性があるかもしれません。国の検査場に持ち込んだら合格する可能性があるかもしれません。
しかし、明らかにダメなケースなのか、グレーだからダメなのかの判断は非常に難しいと思いますので、インターネットなどで検索してみてもいいかもしれません。
整備工場に悪意は無い
整備工場側に悪意はありません。
合格すると知っていて、不合格と説明するケースはまずありません。そんなことをしても整備工場には利益がないからです。
「車検がとおらない」と整備工場に言われた場合、明確な理由があり、「基本的には絶対である」ということを理解してください。
以上、車検の合格・不合格、整備工場によって判断が違う理由の記事でした。