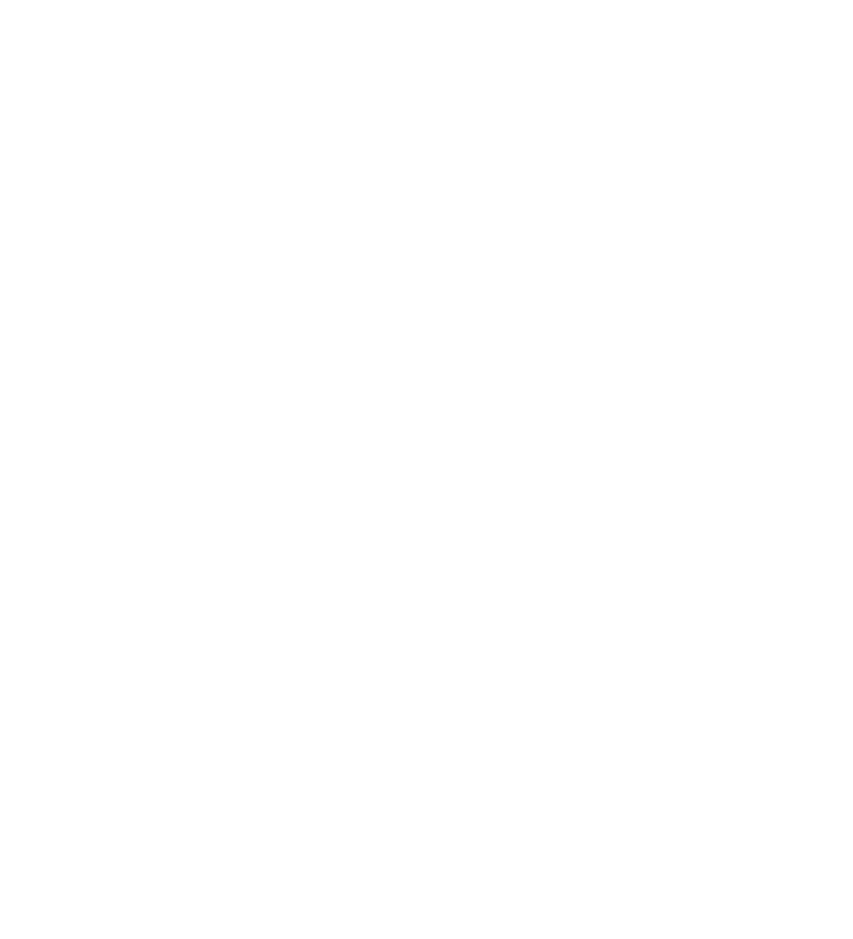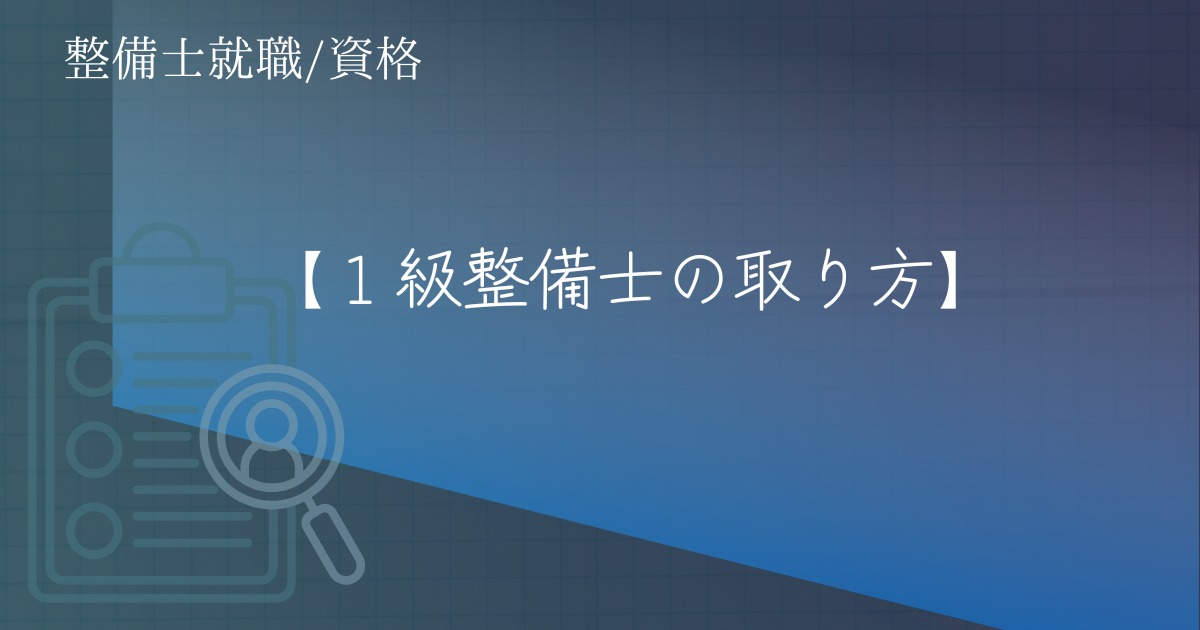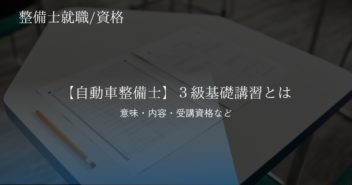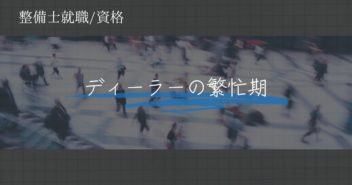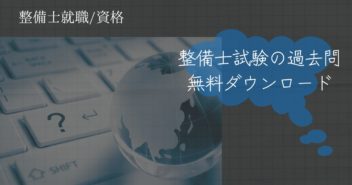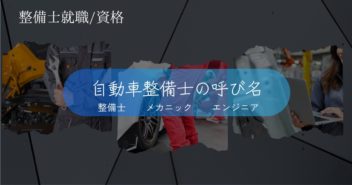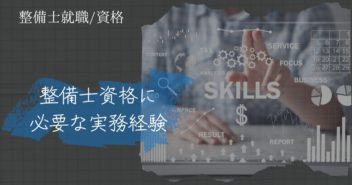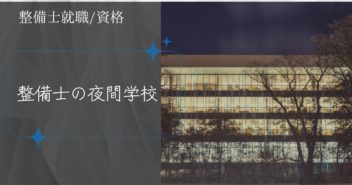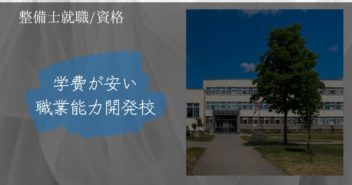- 1級自動車整備士の資格を取る方法が知りたい
- 1級自動車整備士の受験資格が知りたい
一級整備士の資格を持つ人は周りにそれほど多くいないため、取得方法がよくわからない現役整備士の人も数多くいます。また、現在高校生などで、自動車整備士最高峰の国家資格である「一級整備士」の資格取得を視野に入れて、専門学校への進学等を考えている人もいると思います。
この記事では、一級整備士の資格を取る方法や受験資格について、業界経験の豊富な一級整備士の管理人が詳しく説明します。
この記事に書いた一級整備士は「一級小型自動車整備士」のことで、「一級大型」や「一級二輪」のことではありません。現在、一級「大型」自動車整備士の資格試験は実施されていませんので、一級と言えば、一般的に一級小型のことを指します。なお、この記事で書く「二級整備士」とは「二級ガソリンまたは二級ジーゼル」を指し、「二級二輪」には当てはまりません。一級小型自動車整備士を取得するためには、二輪の資格は必要なく、有利になることもありません。
この記事を書いた人:きりん
元ディーラーの一級整備士で整備士ねっと管理人です。自動車整備業界に長く携わり、現在は整備業界のコンサルなども行っています。twitterでたくさんの整備士さんや業界の人と繋がっているのでチェックしていただけるとうれしいです。(seibisi_net)
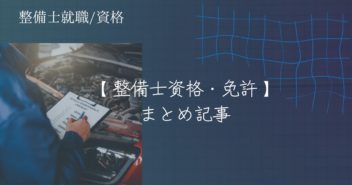
一級整備士試験の受験資格
- 二級整備士合格後、3年以上の実務経験がある者
- 自動車整備専門学校の「1級課程」卒業者
上記、いずれかの条件が当てはまる人が、一級整備士の試験を受験することができます。
一級整備士3つの試験
一級小型自動車整備士の資格を取るためには、一級小型自動車整備士のそれぞれの「学科試験」と「実技試験」に合格する必要があります。また、学科試験には「筆記試験」と「口述試験」があります。
| 試験の定義 | 実際の3つの試験 |
|---|---|
| 学科試験 | ①筆記試験 と ②口述試験 |
| 実技試験 | ③実技試験 |
一級を取得するためには上記、①~③の3つの試験に合格しなければなりませんが、基本的には①→②→③の順番で受験する必要があるので、受験資格については、最初に受験する「①筆記試験」の申請時に詳しく審査されます。
一級整備士の試験のみ、試験官と対話方式で試験を行う「口述試験」があります。一級には説明能力や接客能力が必要とされているからです。
一級整備士の資格を取得する2つの方法
- 1.働きながら一級を取得する方法
- 2.学校に通って一級を取得する方法
なお、「2.学校に通って一級を取得する方法(自動車整備専門学校「1級課程」卒業者)」は、「③実技試験」が免除されるとともに、本来、二級取得後に必要な3年の実務経験も必要ありません。
それではこの二つの方法について、詳しく説明します。
1.働きながら一級を取得する方法

- 二級整備士の資格を取ってから3年間働く
- (整備振興会の講習に通う→実技試験免除したい場合)
- 学科試験(筆記)に合格する
- 学科試験(口述)に合格する
- (実技試験に合格する→講習に通わない場合)
- 両免申請(全部免除申請)をする
実際に働きながら一級を目指す人は、上記の順番で一級を取得します。
実技試験は、振興会の講習に通い、修了すると免除されるので、実技試験にチャレンジするか、振興会の講習に通うのかを選択できます。また、この場合、講習を受けるタイミングについては、学科試験や実技試験の前でも後でも良いこととなっています。
- 二級を取得後3年働く→学科試験(筆記・口述)に合格→実技試験に合格→一級取得
- 二級を取得後3年働く→学科試験(筆記・口述)に合格→振興会講習を修了→一級取得
実技試験の免除
実技試験は、振興会の講習に通うと免除される
前述の通り、働きながら一級整備士の資格を取得するためには、学科試験(①筆記+②口述)と③実技試験に合格しなければなりません。しかし、全国の整備振興会で行われている「二種養成講習(一級過程)」を修了すると、「③実技試験」が免除され、「①筆記試験と②口述試験」に合格するとよいことになります。
働きながら一級整備士の資格取得を目指す人の多くが、整備振興会の講習に通い実技試験の免除を受けています。私も整備振興会の講習に通い、実技試験免除で一級整備士の資格を取りました。
「学科試験」についての免除規定はありませんので、誰でも必ず受験して合格しなければなりません。
なお、一級の実技試験はそれなりに難しく、そう簡単ではありません。
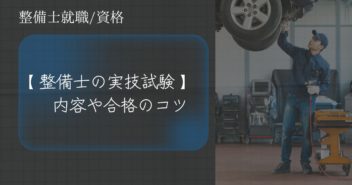
整備振興会の講習を受講する場合にも、受講資格が有り、多くの振興会で「2級ガソリンと2級ジーゼル」の両方の資格を取得していることが条件となっています。また、一級の講習は常時必ず実施している振興会は少ないので、詳しくは最寄りの各都道府県の自動車整備振興会にお問い合わせください。
実務経験
二級を取得してから、3年以上整備士として働いたもの
この場合の二級とは「二級ガソリン」と「二級ジーゼル」を指し、どちらかを持っていれば受験できます。「二級シャシ」と「二級二輪」は当てはまりません。一級の受験には二級ガソリン、または二級ジーゼルの資格が必要です。
実際に受験する際には、「二級整備士の合格証」と「二級を取ってから、3年以上整備士の仕事をしていたことを証明する書類」を提出しなければなりません。
また、3年の実務経験については、2級のように短縮規定がないため、どの大学や学校を卒業しても誰でも必ず3年の実務経験が必要です。
「2級を取ってから、3年以上整備士の仕事をしていたことを証明する書類」は働いている(いた)整備工場の経営者等より証明してもらうもので、「実務経験証明書」と呼ばれています。
関連記事>>>整備士資格の実務経験とは/証明書の書き方
両面申請についてはこちらの記事を参考にしてください。
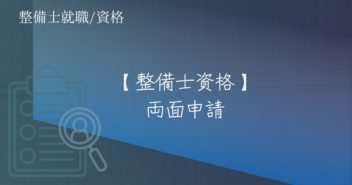
2.学校に通って一級を取得する方法
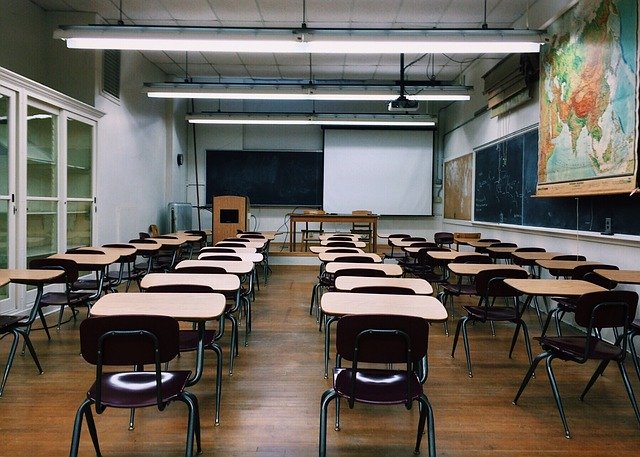
- 自動車専門学校「1級整備士課程」に入学(無資格・未経験で可)
- 4年間就学し卒業(→1級実技試験免除)
- 学科試験(筆記試験・口述試験)に合格する
- 両免申請(全部免除申請)をする
自動車整備専門学校等の「一級自動車整備士課程」を修了すると「実技試験」が免除されます。また、同時に3年の実務経験も免除されます。
但し、専門学校に通っても「学科試験」は免除されないので、筆記試験と口述試験には合格する必要があります。
4年学校に通う→卒業時期の学科試験(筆記・口述)に合格→一級取得
従って、学科試験に合格できない場合があるため、専門学校に通ったからといって、確実に一級整備士の資格が取れるわけではありません。実際に専門学校に通って一級取得を目指していたのに、卒業後2年間の期限のうちに学科試験に合格できず、取得できない人も少なからずいます。
専門学校卒業者でも、一級の学科試験(筆記試験)の合格率は50~80%程度で、まじめに通わなければ合格できません。他の業種の国家試験に比べても非常に難易度の高い試験と言えます。
一級整備士の合格率についてはこちらの記事を参考にしてください。
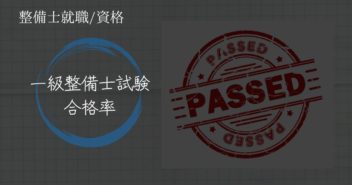
一級整備士課程は2パターン
- 専門学校や大学の「一級整備士課程(4年間就学)」に入学する方法
- 専門学校や大学の「二級整備士課程(2年間就学)」に入学し、卒業した後に「一級整備士課程」に進学する方法
自動車整備専門学校「一級整備士課程(4年間就学)」に入学(進学)する方法は、上記の2つです。主に高校卒業と同時にこちらに入学する人が多いですが、20代前半であれば、高校卒の現役じゃない人も少なからずいます。
1も2も、それほど変わりありませんが、「2.」は二級整備士課程を優秀に終了した者で、進学を希望する者のみを一級整備士課程に進学させるシステムを取っている学校です。高等学校の「専攻科」のような取扱いに似ています。
すでに、二級整備士として働いている人が一級整備士科に入学するケースはあまり聞いたことがありませんが、専門学校のHPなどを見ると、一度働いて二級整備士の資格をとった後に、一級整備士課程の3年生に編入できる学校もあるようです(3年次編入)。
一般的には「学校で一級を取得するのは、働いたことがない学生ばかり」だと思います。このあたりは、専門学校に問い合わせてください。
また、一級課程の就学の期間は4年です。高校を卒業してすぐ専門学校に入学すれば、22歳で卒業と同時に一級整備士となることができます。
一級整備士課程では、2年生の最後に二級整備士(ガソリン・ジーゼル)の資格を取得するため、万がいち、一級整備士の試験に落ちてしまっても、二級整備士として働くことができます。
働きながらと学校に通う方法のどちらが良いのか

| 一級の取得方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 働きながら一級 | ・取得までの費用が抑えられる ・技術を身に付けながら効率よく取得できる ・収入を得ながら取得できる | ・環境にや状況によって挫折する可能性高い ・取得までの期間が長い |
| 学校で一級 | ・取得するまで早い ・取得しやすい | ・高額な費用がかかる ・早く働いたほうが技術が身につく |
働きながら一級を目指す場合、一級を取得するまでに「二級取得後3年」の実務経験が必要であり、学校で二級を取得した人は最低でも4年程度、三級から取得する人は、スムーズにいって7~10年かかります。専門学校卒業者は、実務経験が必要ないため、一級を取るまでの時間が大幅に短縮できるというメリットがあります。
20代で一級整備を取得している人の多くが、専門学校を修了した人です。
一方で、専門学校は高額な費用がかかることや、その割にそれほど技術が身につかないというデメリットがあります。技術が身につかないかどうかは、人にもよりますが、一級を取るために二年間勉強していた人と、ディーラーなどの現場で働いていた人を比べると、働いていた人の方が、その時点では技術が高いことは理解しやすいと思います。
整備士の現場は実力社会です。学校で一級を取得して入社した人でも、それまで働いていた先輩より仕事ができるということは通常あり得ません。また、個人の評価や待遇、その後の出世も、整備士の級で大きく変わることはあまりなく、仕事ができるかどうかで決まる現実があります。このことを頭に入れながら、一級課程の学校の入学を考えましょう。
まとめ
- 働きながら一級を取得する方法
- 学校に通って一級を取得する方法
一級を取得する方法は上記2つです。
- 二級取得後3年働く→学科試験(筆記・口述)に合格→実技試験に合格→一級取得
- 二級取得後3年働く→学科試験(筆記・口述)に合格→振興会講習を修了→一級取得
・4年学校に通う→卒業時期の学科試験(筆記・口述)に合格→一級取得
以上、一級小型自動車整備士の資格取得方法と受験資格でした。